2019年改定版「養育費・婚姻費用算定表」完全解説:離婚時の養育費計算が変わった!
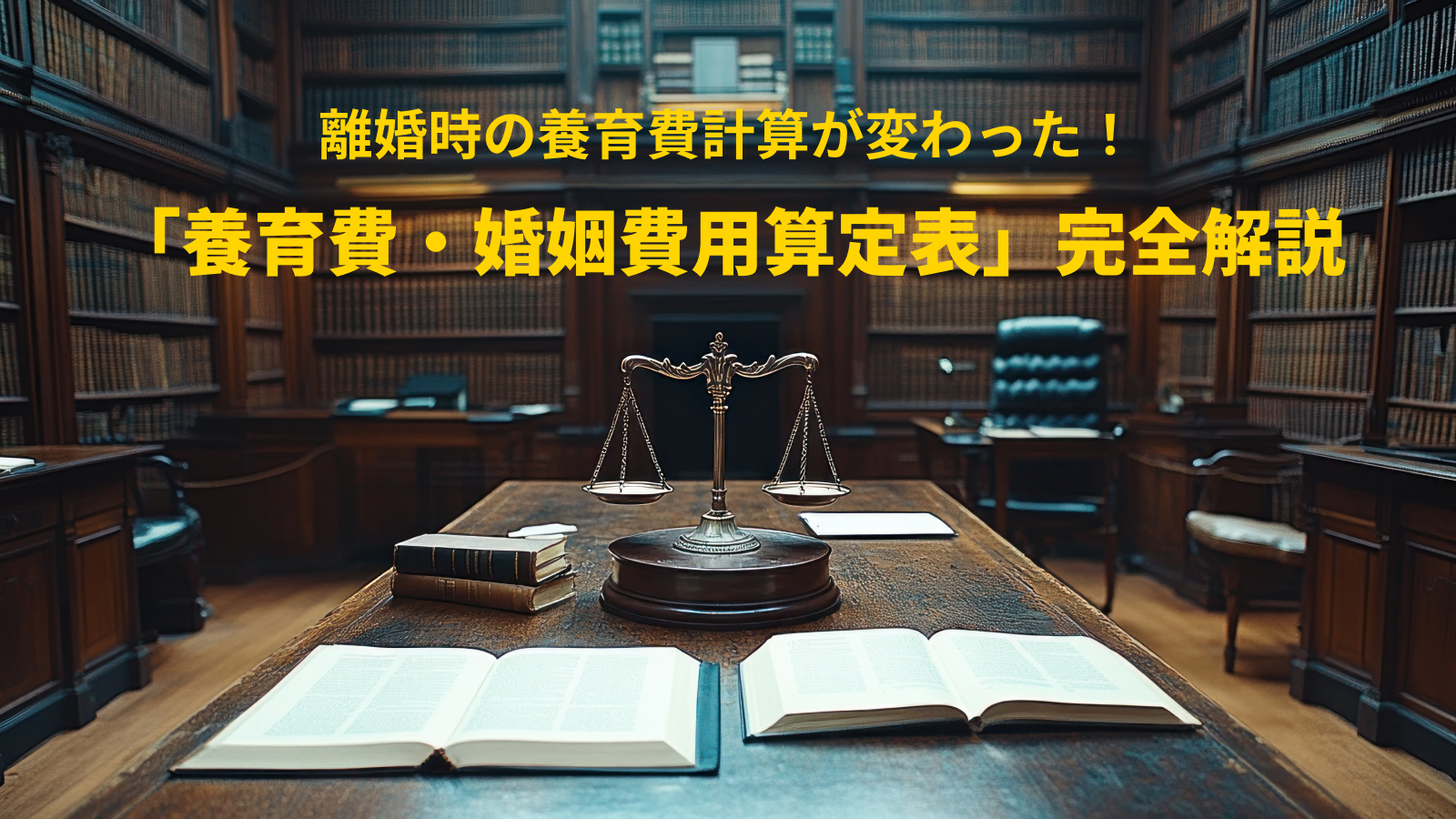
目次
離婚を検討している方、または既に離婚手続きを進めている方にとって、子どもの養育費をどのように決めるかは最も重要な問題の一つです。「相手にいくら請求できるのか」「自分はいくら支払う義務があるのか」といった疑問を抱える方は少なくありません。
実は、これらの疑問に対する答えは、裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」に明確に示されています。しかし、この重要な情報がまだまだ一般的に知られていないのが現状です。さらに、2019年12月23日に最高裁判所司法研修所から発表された改定により、養育費の算定基準が大幅に変更されました。
この改定によって、多くのケースで養育費の支払い額が増加する傾向にあり、離婚を検討している方々にとって非常に重要な変更となっています。
養育費算定表とは何か
養育費算定表の基本概念
養育費算定表は、離婚時における子どもの養育費を公正に算定するため、裁判所が作成した標準的な計算表です。この表は、以下の要素を基に養育費の目安を示しています:
- 義務者(養育費を支払う側)の年収
- 権利者(養育費を受け取る側)の年収
- 子どもの人数
- 子どもの年齢
算定表の法的意義
この算定表は単なる参考資料ではありません。家庭裁判所での調停や審判において、養育費を決定する際の重要な基準として活用されています。協議離婚においても、この算定表を参考にすることで、公平で合理的な養育費の取り決めが可能になります。
算定表の種類と構成
算定表は、子どもの年齢と人数に応じて複数の表に分かれています:
子どもの年齢区分:
- 0歳~14歳(義務教育終了まで)
- 15歳~19歳(高校卒業まで)
子どもの人数:
- 1人の場合
- 2人の場合
- 3人の場合
これらの組み合わせにより、様々な家庭状況に対応した算定表が用意されています。
2019年改定の背景と意義
改定の必要性
旧算定表は2003年に作成されたもので、16年間という長期間使用されてきました。しかし、この間に以下のような社会情勢の変化が生じていました:
① 物価上昇と生活費の変化
- 消費税率の引き上げ(5%→8%→10%)
- 教育費の上昇
- 生活必需品の価格上昇
② 子育て費用の実態変化
- 習い事や塾費用の一般化
- デジタル機器の必要性増加
- 医療費や保険料の変化
③ 働き方の多様化
- 女性の社会進出促進
- 共働き世帯の増加
- 非正規雇用の拡大
改定の主な内容
2019年の改定では、以下の点が主に見直されました:
① 基礎収入の見直し 養育費算定の基礎となる「基礎収入」の計算方法が変更され、より現実的な生活費を反映するようになりました。
② 子どもの生活費指数の変更 子どもの年齢に応じた生活費指数が見直され、特に教育費の増加が反映されました。
③ 算定方法の精緻化 計算方法がより詳細になり、個別の事情により適切に対応できるようになりました。
新旧算定表の比較と変更点
具体的な金額の変化
改定前後での養育費の変化を具体例で見てみましょう:
【ケース1】
- 義務者(父親)年収:300万円
- 権利者(母親)年収:75万円
- 子ども:2人(0歳~14歳)
旧算定表:月額2~4万円 新算定表:月額4~6万円 増加額:約2万円の増加
【ケース2】
- 義務者(父親)年収:500万円
- 権利者(母親)年収:100万円
- 子ども:1人(15歳~19歳)
旧算定表:月額4~6万円 新算定表:月額6~8万円 増加額:約2万円の増加
【ケース3】
- 義務者(父親)年収:800万円
- 権利者(母親)年収:200万円
- 子ども:2人(1人は0~14歳、1人は15~19歳)
旧算定表:月額10~12万円 新算定表:月額12~14万円 増加額:約2万円の増加
変更の傾向と特徴
新算定表では、以下のような傾向が見られます:
① 全体的な増額傾向 ほぼすべてのケースで養育費が増額されており、特に子どもが複数いる場合の増額幅が大きくなっています。
② 高校生年代の養育費増加 15歳~19歳の子どもに対する養育費が特に大幅に増額されています。これは、高校生の教育費や生活費の実態を反映したものです。
③ 所得格差による影響 義務者と権利者の所得格差が大きい場合、養育費の増額幅も大きくなる傾向があります。
算定表の使い方と注意点
基本的な使用方法
① 年収の確認 まず、義務者と権利者の年収を正確に把握する必要があります。ここでいう年収は、税込みの総支給額(源泉徴収票の「支払金額」欄)を指します。
② 該当する表の選択 子どもの人数と年齢に応じて、適切な算定表を選択します。
③ 交点の確認 縦軸(義務者の年収)と横軸(権利者の年収)の交点を確認し、養育費の範囲を読み取ります。
自営業者の場合の注意点
自営業者の場合、年収の算定がより複雑になります:
① 所得の算定 確定申告書の「所得金額」をベースに算定しますが、実際の生活費に近い金額を算出するため、各種控除の加算が必要な場合があります。
② 経費の取り扱い 事業所得の場合、必要経費の内容によって実際の可処分所得が大きく異なるため、個別の検討が必要です。
算定表の限界と個別事情の考慮
算定表はあくまで標準的な目安であり、以下のような特別な事情がある場合は、個別に調整が必要です:
① 子どもの特別な事情
- 私立学校への通学
- 特別な医療費が必要な場合
- 習い事や塾の費用
② 義務者の特別な事情
- 再婚による扶養家族の増加
- 借金の返済負担
- 特別な支出(介護費用など)
③ 権利者の特別な事情
- 就労が困難な事情
- 特別な収入源の有無
養育費の取り決めと実務上の留意点
協議離婚での活用方法
協議離婚において養育費を取り決める際は、以下の点に注意が必要です:
① 算定表の活用 新算定表を基準として、適正な養育費を算定しましょう。感情的な判断ではなく、客観的な基準に基づく話し合いが重要です。
② 書面化の重要性 口約束ではなく、必ず書面(離婚協議書)で取り決めを明確にしましょう。
③ 強制執行認諾文言の検討 将来の不払いに備えて、公正証書の作成や強制執行認諾文言の付与を検討しましょう。
調停・審判での活用
家庭裁判所での調停や審判では、新算定表が重要な基準として活用されます:
① 調停委員との協議 調停委員は新算定表を基準に話し合いを進めるため、事前に自分のケースでの養育費目安を把握しておきましょう。
② 特別事情の主張 算定表とは異なる金額を求める場合は、その根拠となる特別事情を明確に主張する必要があります。
③ 証拠資料の準備 年収を証明する資料(源泉徴収票、確定申告書など)を確実に準備しましょう。
養育費の変更と将来への対応
養育費の変更事由
一度決定した養育費も、以下のような事情変更があった場合は変更が可能です:
① 収入の大幅な変化
- 転職による収入減少
- 昇進・昇格による収入増加
- 失業や病気による収入停止
② 子どもの事情の変化
- 私立学校への進学
- 大学進学
- 就職や結婚
③ 再婚等による家族構成の変化
- 再婚による扶養家族の増加
- 新たな子どもの誕生
将来の養育費計画
養育費を取り決める際は、将来の変化も考慮して計画を立てることが重要です:
① 子どもの成長に伴う費用増加 特に高校進学時や大学進学時の費用増加を見込んだ取り決めを検討しましょう。
② 定期的な見直し条項 一定期間ごとに養育費を見直す条項を設けることで、社会情勢の変化に対応できます。
③ 終期の明確化 養育費の支払い終期(通常は20歳まで、大学進学の場合は22歳まで)を明確にしておきましょう。
まとめ:新算定表を活用した適切な養育費の取り決め
2019年の養育費算定表改定は、16年ぶりの大幅な見直しであり、現在の社会情勢により適合した基準となっています。この改定により、多くのケースで養育費が増額されることになり、子どもの福祉向上に大きく寄与することが期待されます。
離婚を検討している方、または既に離婚手続きを進めている方は、必ず新算定表を参考にして適切な養育費を取り決めることをお勧めします。また、旧算定表に基づいて養育費を取り決めた方も、事情変更により新算定表に基づく変更が可能な場合があります。
子どもの健全な成長と発達のために、そして公平で合理的な養育費の取り決めのために、新算定表を積極的に活用していきましょう。
■裁判所(養育費・婚姻費用算定表)
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
なお、複雑なケースや特別な事情がある場合は、家庭裁判所の調停や専門家(弁護士等)への相談を検討することをお勧めします。適切な養育費の取り決めは、子どもの将来にとって極めて重要な要素であり、慎重かつ丁寧な検討が必要です。
